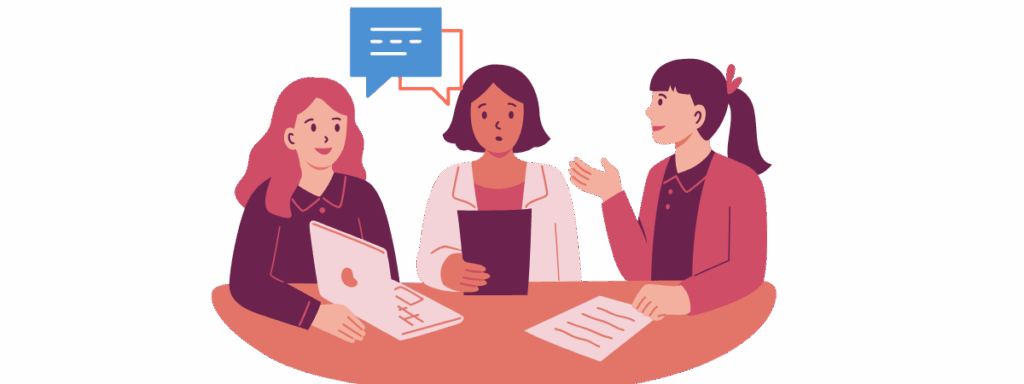担任の先生との相性、大きいですよね。特にお子さんが「学校行きたくない…」なんて言い出したら
親としてはとても不安になりますよね。
そのようなとき、どんなことをしたら良いかまとめましたので、是非参考にして下さいね。
① 「気持ちを言葉にできる環境」をつくる
お子さんが不安や不満を話せる雰囲気を家庭に持つことが第一歩です。
大人が「なにがあったの?」と深刻な表情で聞くと、かえって話しにくくなります。
● 実践ポイント
- 食事中やお風呂など、自然なタイミングで「今日は楽しかったこと、教えて!」などから話を始める
- 否定せずに「そっか」「そう思ったんだね」と共感で返す
- 話したくない日は「話すの、また今度でもいいよ」と無理に聞き出さない
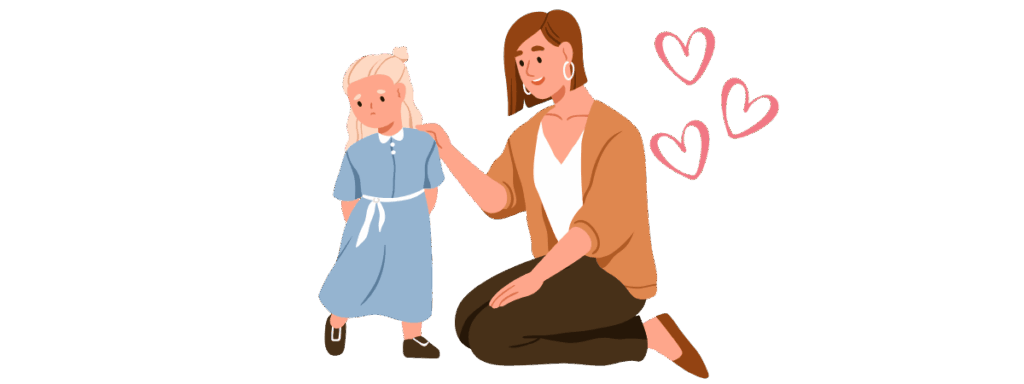
② 「担任の人柄」だけで判断しない習慣を持つ
担任の先生の話ばかりになってしまうと、お子さんも「先生=学校=いやな場所」と感じやすくなります。
● 実践ポイント
- クラスメイトや好きな授業、楽しみな給食など、担任以外のポジティブな要素に目を向けさせる
- 「◯◯ちゃんとまた遊べるね」「今日は図工あるね!」とポジティブな視点を声かけで示す
- 担任のことを親が悪く言わない(たとえ本音では合わないと思っていても)
子どもは、親の言葉の影響をものすごく強く受けます。
親が担任を否定すると、子どもも担任の言う事を聞かなくなり悪循環に陥ります。
担任のことをよく思っていなくても、子供の前では悪く言わないほうが無難です。
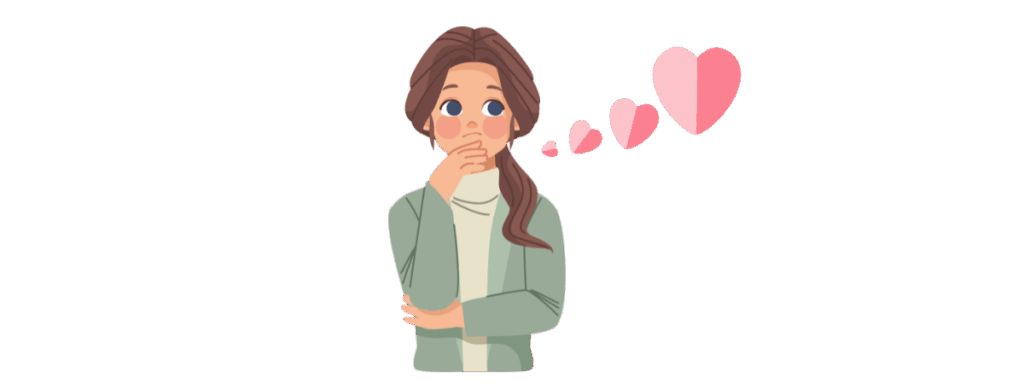
③ 「安心できる時間」を毎日に取り入れる
学校で緊張している子は、家ではリラックスできる時間が不可欠です。
● 実践ポイント
- 学校から帰ったら「5分間おひざタイム」など、親子で安心できる時間をルーティンにする
- 好きな遊びや動画を一緒に楽しむなど、笑顔になれる時間を意識的につくる
- 夜寝る前に「今日よくがんばったね」と労う習慣をつける

④ 「小さな成功体験」を積ませる
担任との相性が悪くても、別の場所での達成感が「学校に行こう」という気持ちにつながります。
● 実践ポイント
- 学校で「今日ひとつチャレンジしてみよう」と朝に目標を決める(例:挨拶する、手を挙げる)
- 家で「昨日より1問多くプリントできたね」など、学習面で達成感を持たせる
- 習い事や家庭内の仕事(お皿洗いなど)で自信を持たせる
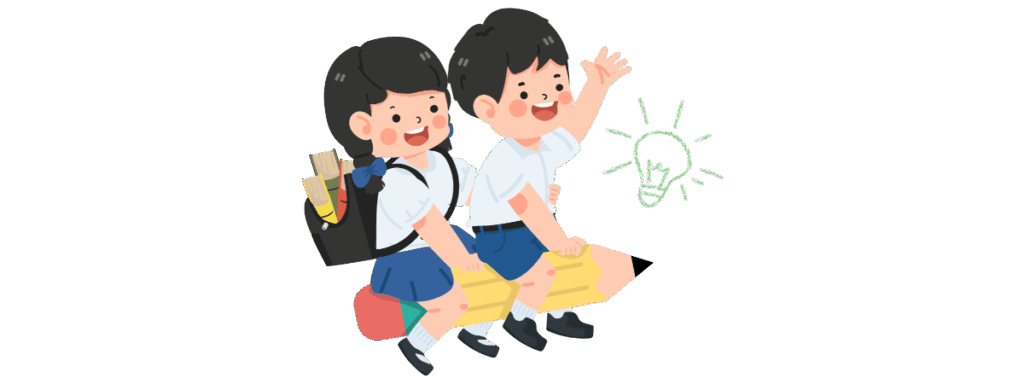
⑤ 必要なら「親が先生とつなぐ」役割を担う
無理に我慢させるのではなく、先生に相談することも大事です。
その際は、お子さんの気持ちが伝わるように、感情的にならず丁寧に伝えましょう。
● 実践ポイント
- 連絡帳や面談で「本人はこんなふうに感じているようです」と事実を穏やかに共有
- 「こうした声かけをしていただけるとありがたいです」と具体的なお願いにする
- 担任が難しければ、養護教諭(保健室の先生)やスクールカウンセラーなど他の支援者に相談する

⑥養護教諭(保健室の先生)やスクールカウンセラーなどに相談する場合の手順
養護教諭(保健室の先生)やスクールカウンセラーなどに相談するといっても
どうやって相談するの?
誰に声をかけたらいいの?
と悩みますよね。具体的な相談方法を以下にまとましたので、参考にして下さいね。
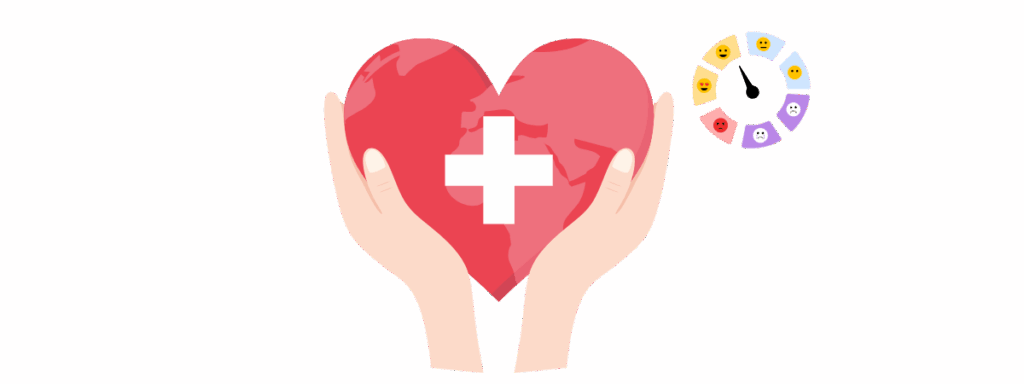
① まずは学校に電話でアポイントをとる
いきなり訪問するよりも、あらかじめ連絡しておくことで、支援者の準備や時間確保ができます。
● 伝えるポイント
- 担任の先生が授業中に、管理職宛に電話をかける
- 「担任の先生とは別に、◯◯について相談できる方はいらっしゃいますか?」
- 「子どものことで一度お話を聞いてほしいのですが…」
- 「カウンセラーさん(または保健室の先生)に相談できますか?」
※スクールカウンセラーは非常勤で、週1〜2日しかいない場合も多いので、在校日を確認しましょう。
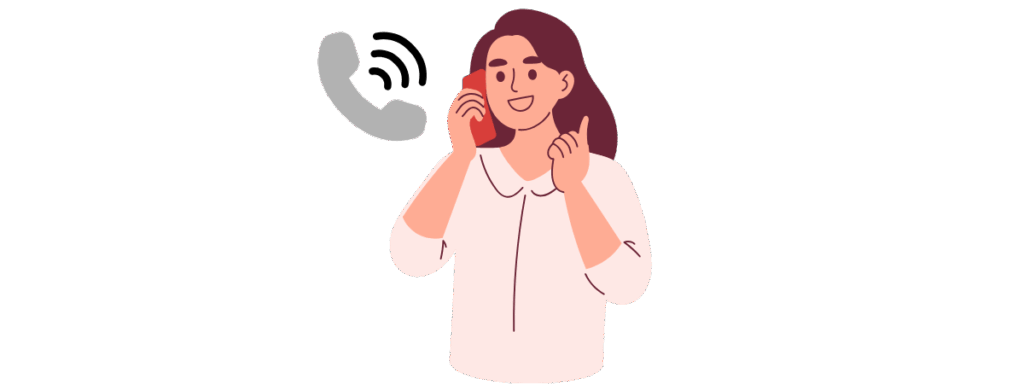
② 相談当日は、落ち着いて「事実ベース」で話す
感情的になりすぎず、「こんなことがあった」「子どもがこう感じている」と具体的に伝えます。
● 話すときのコツ
- 子どもの口から聞いたこと、家庭での様子、変化などを整理しておく
- 「担任の先生が悪い」と断定せず、「どう対応していいか悩んでいる」と相談する姿勢で
- 「子どもにとって学校が安心できる場になるようにしたい」と目的を明確に
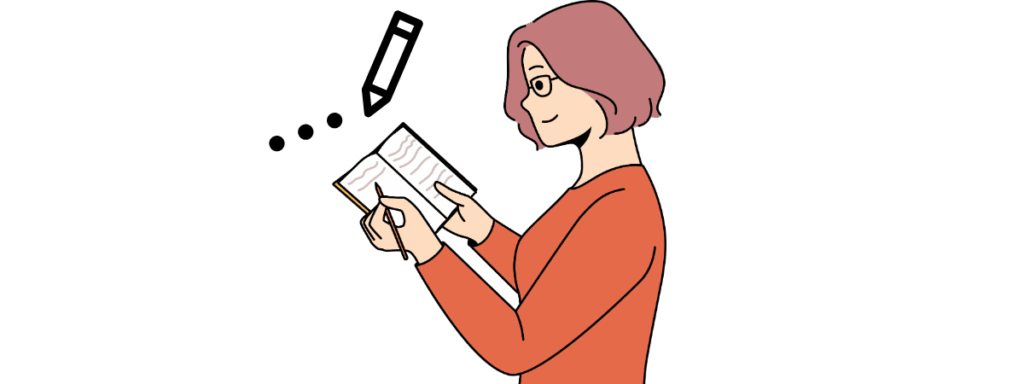
③ 養護教諭に相談する場合
保健室の先生は、日常的に子どもの様子を見ていて、心理的サポートの役割も大きい存在です。
● こんな相談が可能
- 最近よく保健室に行っているけど、様子はどうですか?
- 家で「先生が怖い」と言っていますが、学校ではどんな様子ですか?
- 少しの間、保健室で休ませてもらうことは可能ですか?
※場合によっては、保健室が「避難場所」としての役割を担ってくれることもあります。
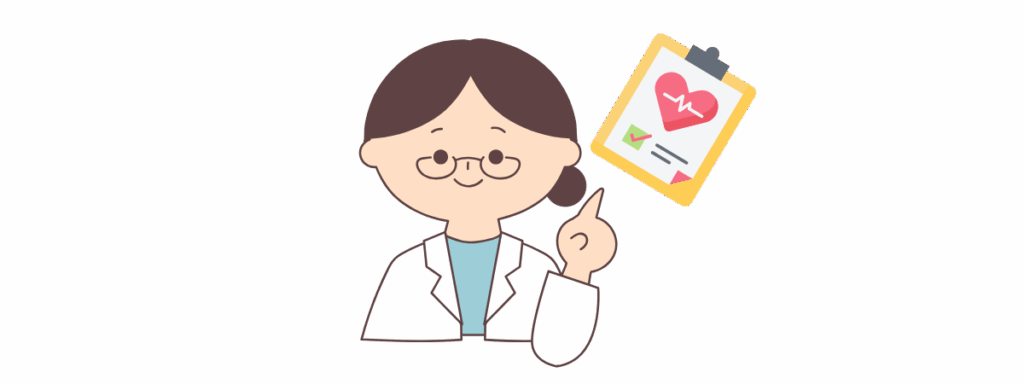
④ スクールカウンセラーに相談する場合
心理の専門家なので、親の不安や子どもの気持ちに丁寧に寄り添ってくれます。
面談時間は30分~1時間が一般的で、予約が必要なことも多いです。
● 相談のポイント
- 子ども本人が同席するか、まずは保護者だけかを選べる(本人が嫌がる場合は無理に連れていかなくてOK)
- 必要に応じて、担任への伝え方も一緒に考えてくれる
- 継続的に相談できることもある(例:毎月1回など)
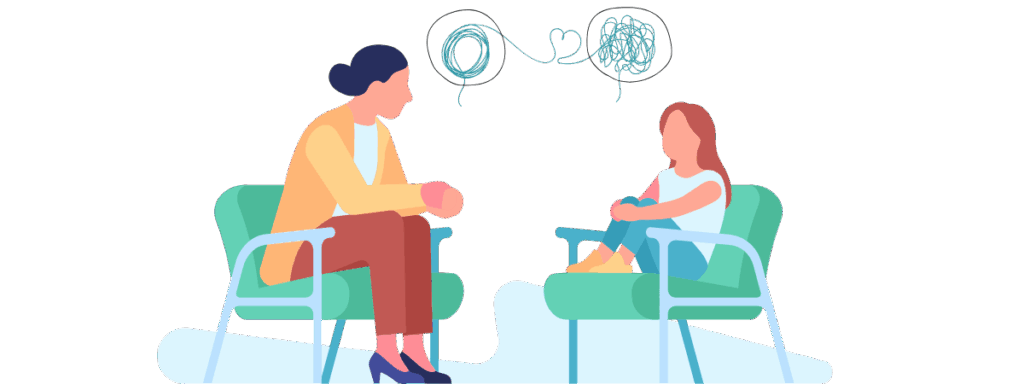
⑤ 相談後の流れ
1回で解決するケースは少ないですが、「子どもに合った対応を一緒に考えてくれる味方」ができるだけで、親も子も安心感が大きく変わります。
● 相談後にできること
- スクールカウンセラーや養護教諭に、今後の子どもの様子を見守ってもらうようお願いする
- 担任の先生との連携が必要な場合、間に入ってもらえるよう頼む
- 家庭でも「相談できる場所があるよ」と子どもに伝える
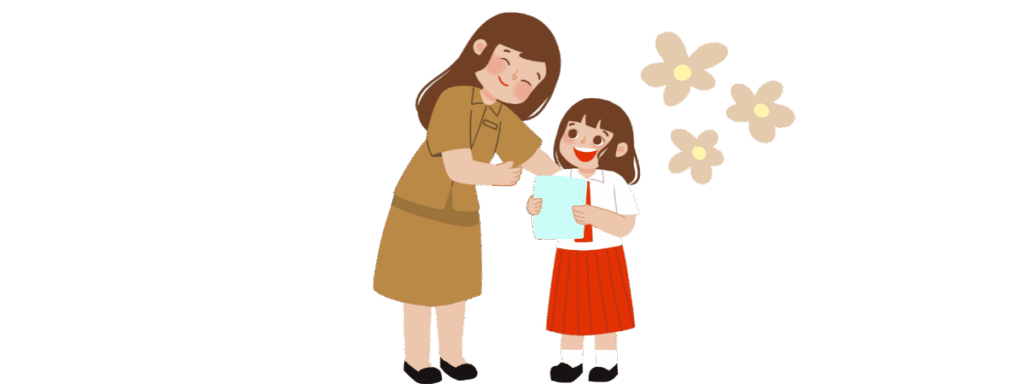
まとめ 【親が一人で悩まない】
保護者の方が不安になってしまうと、その気持はお子さんに伝わります。
なので、保護者の方がまずは安心してお子さんを見守れる心の余裕を持つことが大切です。
一人で悩まず、学校には味方になってくれる先生がたくさんいるはずです。
- 親が一人で悩まず、他の先生にも相談してみる。
- 「学校がいや」と言えるのは、信頼できる親がいる証。まずは安心感を大切に。
- 先生との関係がすべてではなく、学校には他にもたくさんの「楽しい」「得意」があります。
- 親が冷静に受け止め、焦らず、少しずつ「行ってもいいかな」の気持ちを育てていきましょう。
- 担任以外にも、学校には「味方」がたくさんいます
- 一人で抱え込まず、早めに相談することで悪化を防げます
- 養護教諭・スクールカウンセラーの力を借りることは、「子どもを守るための立派な行動」です