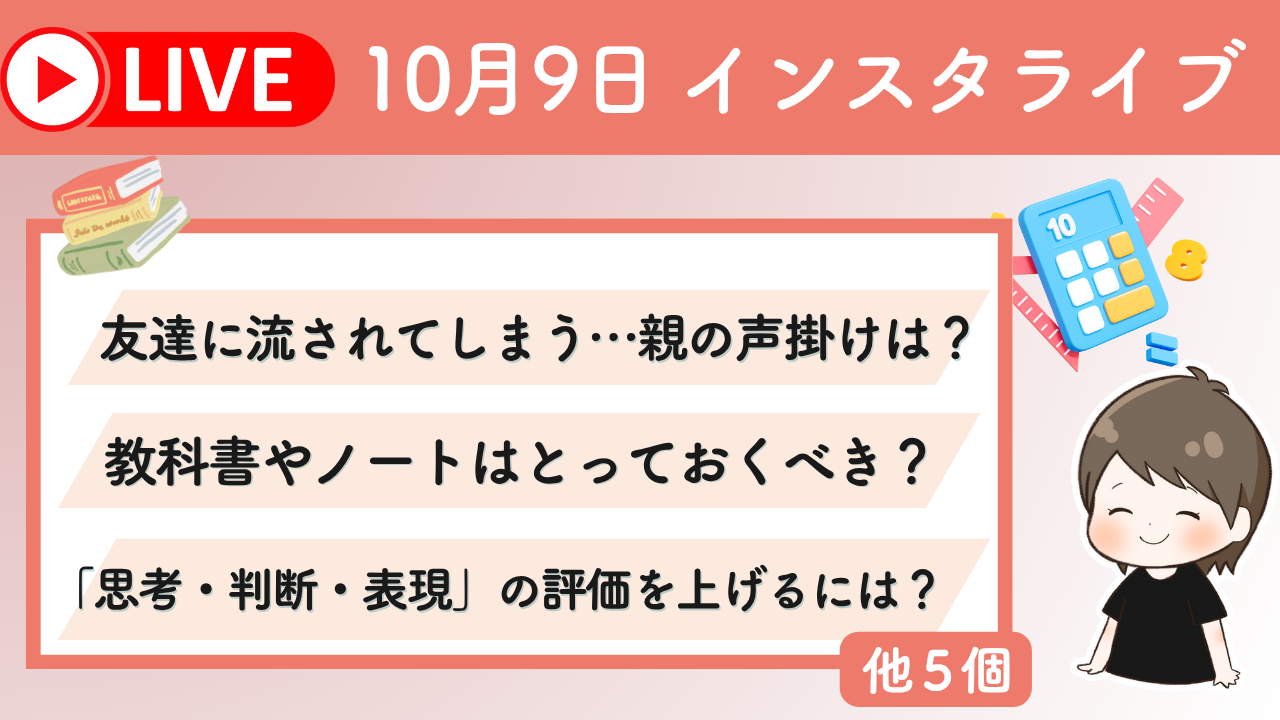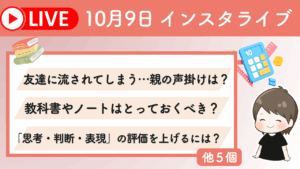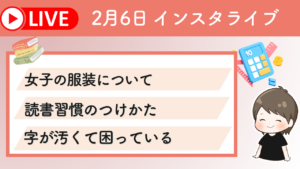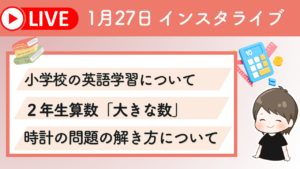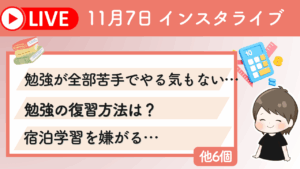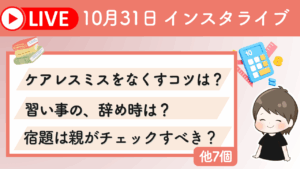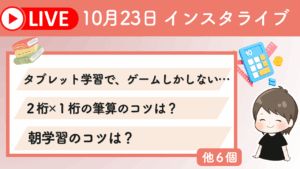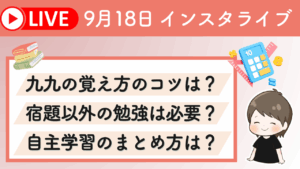今回のライブ配信では、
友達に流されやすいお子さんへの対応や、
家庭での教科書・プリント管理、国語の評価を上げる工夫など、
実践的なヒントを紹介。
また、ライブ中の質問では音読速度、読解力、コンパス操作、九九など、
家庭で支援できるポイントを整理しました
友達に流されやすい小3男子への対応
小学校3年生頃の男子は「ギャングエイジ」と呼ばれる時期に入り、
仲間との関係を強く意識するようになります。
これは自然な発達の一環であり、過度に叱ったり抑え込んだりする必要はありません
子どもの行動を「悪い」と決めつけない
「友達の真似をしてばかり」「周りに流される」と感じても、
それは「社会性を学んでいる途中」でもあります。
むしろ大切なのは、その行動の意味を理解してあげることです。
子どもたちは複雑な人間関係で日々過ごしており、子どもたちには子どもたちの社会があります。
あまり過度に干渉しすぎず、かと言って放置しすぎず、
バランスを大切にしながら関われると良いと思います♫
対話で考えを引き出す
学校と家庭の連携を子どもに見える形で示し、
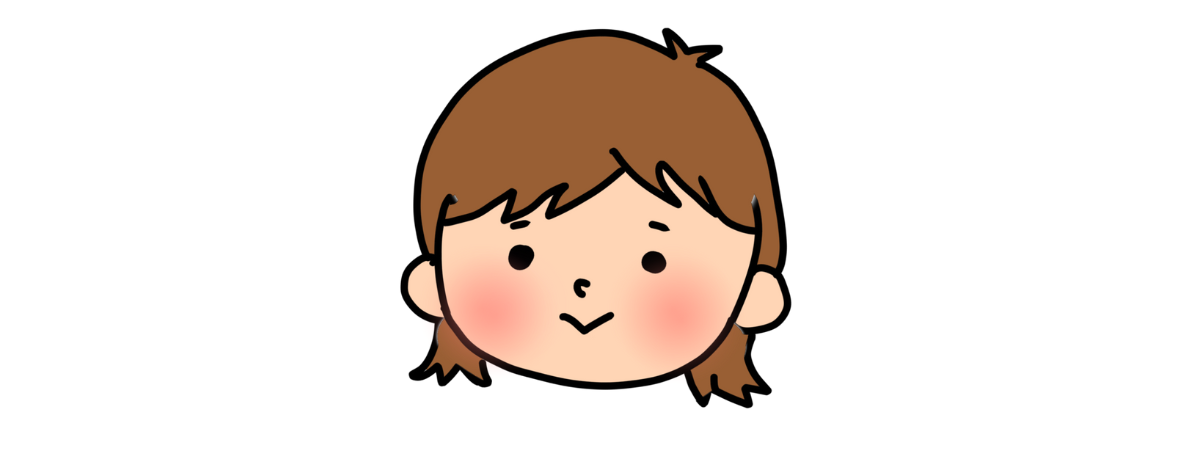
「先生からこう聞いたよ。お母さんはこう思うけど、あなたはどう思う?」
と、考えを言葉にさせましょう。
これにより、自己判断力が育ちますし、親子のコミュニケーションにもつながります。
エネルギーを発散させる工夫
ギャングエイジの男の子は行動エネルギーが高いため、抑えるよりも「発散」させることが大切だと思います。
好きなことや、スポーツ、創作活動などにエネルギーを向けることで、けじめを覚えながら自立も育ちます!


教科書・ノート・プリントの保管と活用法
家庭で「どの教材を残すべきか迷う」という声も多く聞かれました。
整理のポイントを教科別にまとめます。
教科書
- 国語:音読や持ち帰り忘れ対策として家庭常備が便利です
- 算数:宿題や通信教材の見直し時にすぐ確認できるため、家庭用に1冊あると安心です。
- 生活・図工:作品づくりの際にイメージを共有するのに役立ちます。
- 道徳:思考を促す読み物として、就寝前の読み聞かせにもおすすめです。
ノート
余白があるものは再利用ができます♫
自主学習ノート、長期休みのドリル解答スペース、筆算の学習の時の補助などに活用できます。
プリント
原則として破棄して良いと思います。
ただし、「漢字まとめプリント」などの復習に使えるものは保管しておくと便利です。
長期休みに苦手確認に役立ちます。
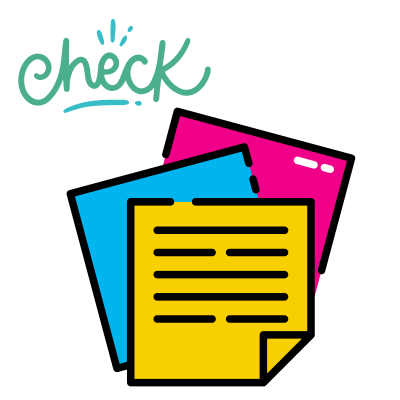
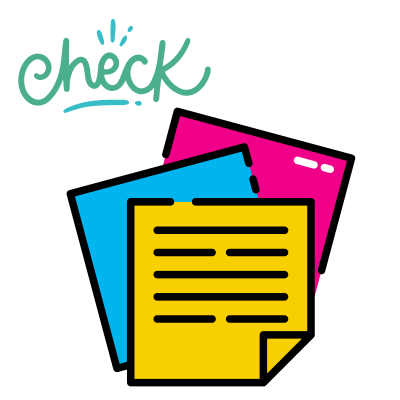
国語の「思考・判断・表現」評価を上げるには(小2男子)
「いつもB評価が続く」
「Aを取るにはどうすればいい?」
という相談もありました。
評価の仕組みを理解する
国語の「思考・判断・表現」は、授業内容の理解に加えて
安定してカラーテストで高得点を取ることが必要です。
つまり、テストで「記述問題を丁寧に書ける」力が求められます。
家庭でできる具体策
- 授業内容の定着を最優先に
学校の授業を集中して聞く姿勢が最も重要です。 - 教科書準拠ドリルで反復練習
「教科書ワーク」や「ぴったりトレーニング」など、使っている教科書会社に対応したものを選びましょう。 - 基礎の徹底でA評価に近づく
発展問題よりも、授業内容を確実に理解・表現できることが評価アップにつながります。
⇩教科書に沿ったワークはこちらです
ライブ中のQ&A:家庭でできる実践支援
音読が速すぎる小1女子への声かけ
速読は悪いことではありませんが、内容理解が浅くなることもあります。
家庭では次の工夫をしてみましょう。
- 交互読みで親が適切な速度を見せる(「。」がきたら読み手交代)
- 合唱読み(一緒に声を出す)でペースを共有
- 手拍子やリズムでテンポを体感する
「今の速さだと聞きやすいね」といったフィードバックで、
感覚的に“適切なスピード”を身につけられます。
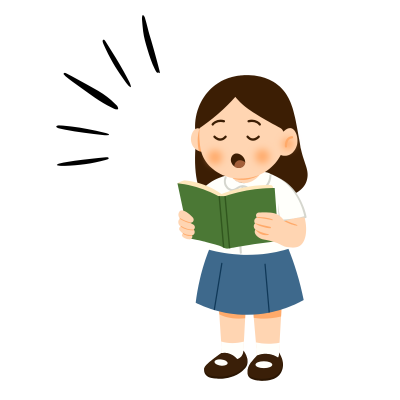
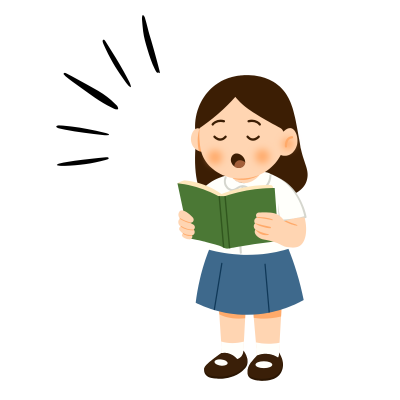
読解力不足(小2中心)のサポート方法
読解力は「読める」だけでなく、「理解して考える力」です。
焦らず段階的に育てましょう!
- 授業重視+準拠ドリルで定着を図る
家庭では、授業の内容に沿ったドリルを少しずつ進めましょう。 - 文章題は親子で一緒に読む
算数の文章題では、設問を一緒に声に出して読み、どんな場面かを共有することが効果的です。 - 語彙・意味理解の補い
間違えた言葉や文をその都度ていねいに説明し、正しい理解を積み重ねましょう。 - 簡単な読物から段階的にレベルアップ
少しやさしめの本を使い、「読めた」という達成感を積み上げることが継続のカギです。
⇩読みやすいおすすめ本
コンパス操作が苦手な小3への練習法
円がうまく描けない場合は、まずコンパスの扱いやすさを見直しましょう。
- 子どもの手に合ったサイズを選ぶ
- 針の固定をしっかり行い、軸を水平に回す
- 模様や花などの自由制作で“楽しく練習”するのがおすすめです。
「正しく描ける」よりも「描くのが好き」を育てることが上達の近道です。
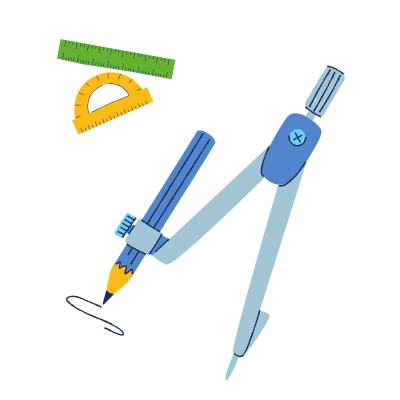
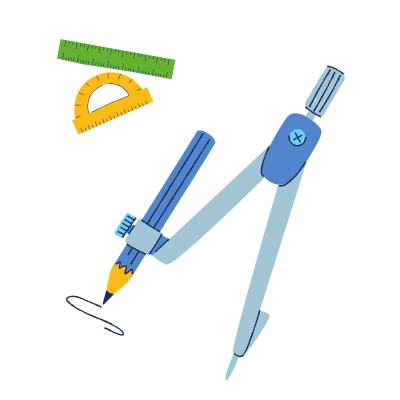
大きな数の概念定着(小2・位取り)
「10が10個で100」「100が10個で1000」という“位の部屋”のイメージを、
具体物で視覚的に理解させましょう。
- お金を使って「1円→10円→100円→1000円→1万円」のつながりを実感。
- 積み木やレゴで「10個で1まとめ」ルールを体験。
- キャラクター付きドリルなどで楽しさを演出。
具体物を使って体験的に覚えることが、抽象的な数の理解につながります。
⇩人気キャラクタードリル
九九の学習をスムーズに進めるコツ
九九は単なる暗記ではなく、「掛け算の意味」を理解することから始めましょう。
- 意味理解を優先する
「3人にリンゴを2個ずつ配る」など、身近な例を使って掛け算の構造を説明します。 - 多チャネルで反復する
歌・カード・ポスター・ゲームなど、楽しく繰り返す方法を組み合わせましょう。 - 早めに誤習得を防ぐ
6の段・7の段での言い間違いはその場で直すようにします。
九九をただ覚えるだけでなく、「考えながら覚える」姿勢を育てることで、計算力全体が安定します。
⇩このあたりオススメです
学びを支えるための家庭の心構え
学習習慣を支えるうえで大切なのは、
「焦らない」「比較しない」「成功体験を積ませる」
ことです。
低学年の子どもは発達の個人差が大きく、
無理に抽象的な学びを押し付けると、
勉強嫌いにつながることがあります。
「できた」「わかった」という小さな積み重ねが、後の意欲と自信につながります!


まとめ
- ギャングエイジの行動は自然な発達。対話で自立を促す。
- 家庭では教科書・ノート・プリントの「取捨選択と活用」を工夫。
- 国語評価を上げるには、授業理解と準拠ドリルの継続が効果的。
- 音読・読解・九九など、日常に取り入れやすい方法で“学びの型”を身につける。
- 焦らず、子どもの発達段階に合わせて成功体験を積み重ねることが、長い目で見て最も大切です。