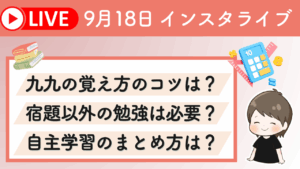目次
🔍さくらんぼ計算とは?
たとえば「8+5」のような繰り上がりのあるたし算を、
「10のまとまりを作る」ために数を分けて考える方法です。
例 8+5
やり方としては…
①「5を2と3に分ける」(引き算)
② 「8+2で10」(足し算)
③「10+3で13」(足し算)
つまり、
ことになりその結果、
- 計算スピードがアップ
- 暗算力の向上
- 数感覚の育成
につながると考えられます。
ただ、保護者の中には

「こんなの、自分が子どものときに習ってないから教えられない!」



「普通に計算したほうが早いのでは?」
とさくらんぼ計算に疑問を持つ方も多いです。なので
🏠家庭でできるサポート5つの工夫を順に紹介していきますね。
①「まずは“なぜやるか”を親が理解する」


保護者も「ただ面倒な方法」ではなく、
10のまとまりを意識するための方法
と理解するとサポートがしやすくなります。
ポイント
- 「10を作る練習なんだね!」と考える
- 普通の計算と混同せず「考え方を育てる時間」と位置づける
②「具体物で、手を動かして体験させる」
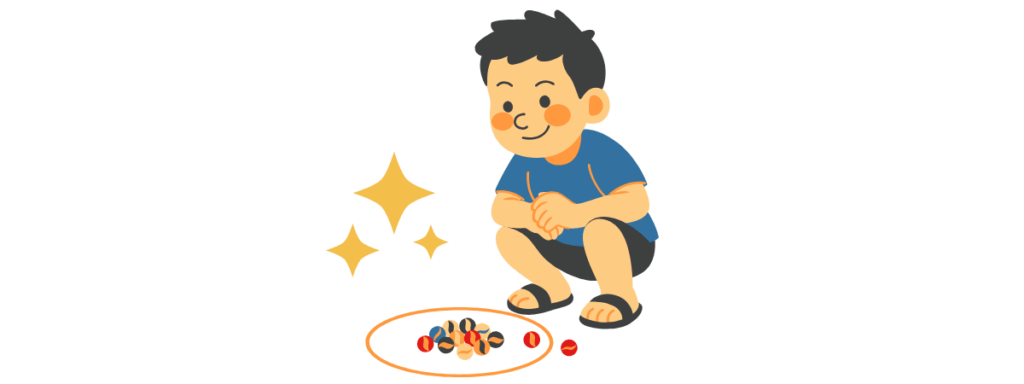
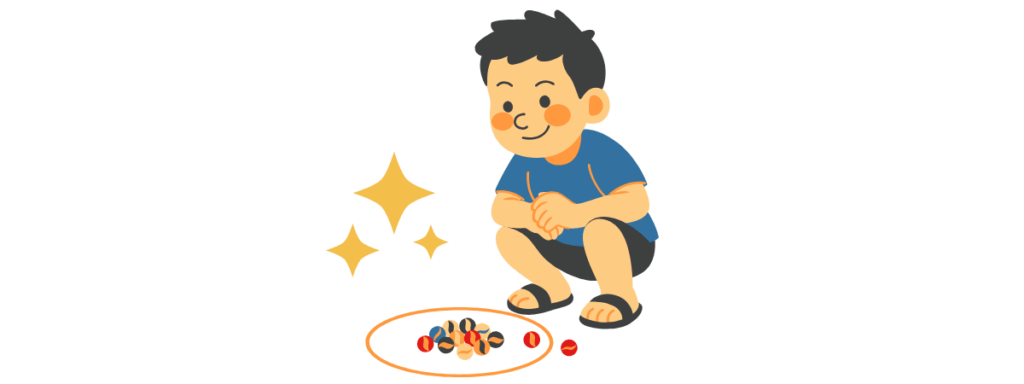
いきなりノートで練習ではなく、
おはじき・お菓子・数字カードなどで
実際に「分けてみる」ことから始めましょう。
声かけ例
- 「8個のアメに、何個足したら10になるかな?」
- 「じゃあ、あと何個残る?」
↓学校で使っていたおはじきに似ています
③「“さくらんぼの形”を一緒に書いてみる」
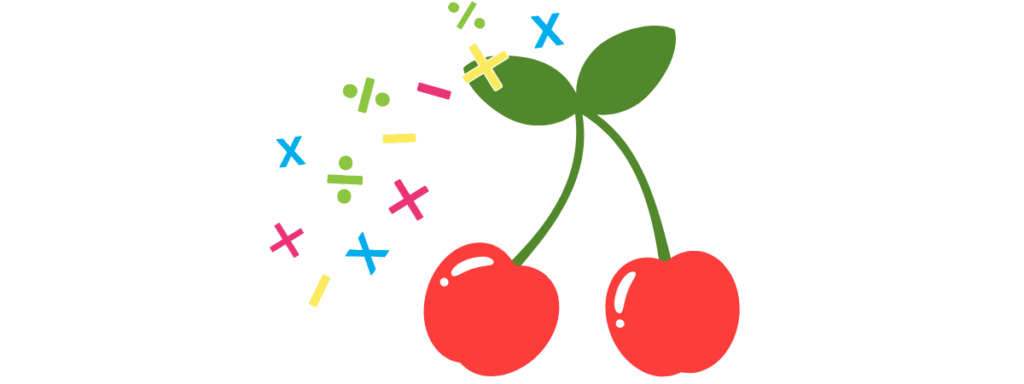
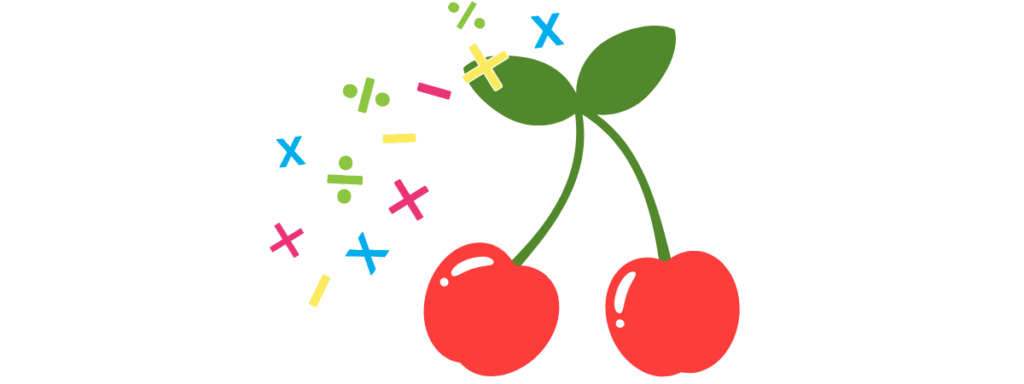
紙に○と線でさくらんぼの形を描いて、
「どの数をどんなふうに分ける?」と一緒に考える時間を作ると、
だんだん子どもも自分でできるようになります。
ヒント
- 「10になるように分ける」がポイント
- ○で囲って枝でつなげることで、視覚的に理解しやすくなる
④「普通の計算との切り替えも大事に」
「さくらんぼ計算だけ」だと混乱する子もいます。
なので、「さくらんぼで考える→ふつうのたし算と同じになる!」
とつなげてあげましょう。
声かけ例
- 「8+5を、ふつうに計算するとどうなる?」
- 「さくらんぼで考えると、同じになるね!」
⑤「苦手なら、“無理に使わせない”のも選択肢」
さくらんぼ計算はあくまで考え方の手助けツールです。
お子さんによっては、逆に混乱する場合もあります。
その場合は…
アドバイス
- 無理に続けさせず、「10のまとまり」が身についたら終了でOK
- 学校で使うときだけ取り組み、家庭では「ふつうのやり方」でもOK
- 最終的に「正しく計算できる」ことが大切!
💬おわりに



「自分の時はこんなやり方なかったのに…」
と思う保護者の方も多いですが、
今の教育では、
とはいえ、すべてのお子さんに合うとは限りません。
その子のペースと理解度にあわせて、必要なところだけ取り入れる
という柔軟な姿勢が一番のサポートになりますよ!