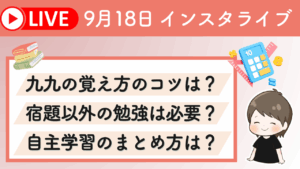「自主学習」は、自由に見えて実はとっても難しい宿題です。

「なにやったらいいの?」



「字がうまく書けないからイヤ…」
とお子さんも戸惑いがちで、
保護者の方も毎回ネタ探しに頭を悩ませていることがよくあります。
そこで今回は、
を、教育現場10年の経験と家庭支援の視点から、具体的にまとめました♫
① 「今の授業」にリンクさせる
自主学習は、授業の理解を深めるためのチャンス。
今習っている教科や単元とつなげることで、先生も「よく見てるね!」と評価してくれます。
- 国語:「習った漢字を使って短文を作る」
漢字は漢字練習ノートに「何度も書いて終わり」というパターンが多いようですが
それでは覚えられません。
一番良いのは「漢字を使って文章を作ること」です!
⇩漢字辞典には例文が載っていることもあります
- 算数:「今日の授業と同じ問題を作ってみる」
子どもたちは問題を「解く」ばかりで、
問題を「出す」側になることはなかなかありません。
問題を「出す」側になると、より頭を使わなければならないので理解がとっても深まります。
- 理科・社会:「授業で出てきた言葉を図鑑や辞典で調べる」
授業では、話を一方的に聞くばかりなので主体的な学習とは程遠いです。
その中でも自分が気になったものを
「主体的に」調べることで本当の意味での「学習」になります✌
⇩図鑑NEOオススメです
② まずは「まねする」からでOK!
自分で考えるのが難しいお子さんには、まずは「まねて学ぶ」ことからスタート。
お友だちやきょうだいのノート例を見ながら取り組んでみるのも効果的です。
- 教科書の問題をそのまま写して、自分で答えをつけてみる
もう1度同じ問題を解くことで、より理解が深まり学習が定着します。
- 教科書のまとめをそっくり書き写すのも立派な学習
授業中は自分のペースで学習できないこともあるので、自宅で落ち着いて改めて学習することできちんと定着することもありますよ。
- 最初は「親と一緒に考える時間」もOK!
最初は何をしたらいいかなかなかわからないこともあると思うので、そういうときは親御さんと一緒にやるとモチベーションもアップ!慣れてきたら、徐々に自分でできるようになりますよ。


③ 「まとめる力」より「書いてみる経験」を重視
最初から上手に構成できる子は少ないので、
見たまま・思ったままを書くことから始めてOK。
書いてみた体験自体が、自信や次のステップにつながります。
- 調べたことを短く箇条書きにするだけでも十分
いきなり長文を書くのはハードルが高い💦
まずは箇条書きから始めてみましょう!
⇩短めの文章問題なので解きやすそう!
- 本や動画の感想を「ひとこと日記」で表現
長文ではなく短文で書く練習から始めると、
すこしずつ文章を書くことに慣れてきます。
⇩かわいい手帳で一言日記を書くのもオススメです
- 最後まで完成させるより、「書いた経験」を褒めてあげる
まずは「書くことにチャレンジ」したことが花丸!
自信をつけてあげましょう!


④ 興味のあることを学びに変える
自主学習の魅力は「好きなことを勉強にできる」ところ。
本人がワクワクしながら書けるテーマを選ぶと、ぐっと集中力が上がります。
- 昆虫や動物、スポーツなどの「大好きなテーマ」で調べ学習
図鑑やインターネット、自分のカメラで写真を取ってノートに貼るのもOK!
- ゲームの攻略法やYouTubeの内容を「まとめノート」に
つい楽しくなって好きなことばかり書きがちですが
「ゲームを知らない先生がみてもわかる、または、ゲームをやりたくなる」
ような気持ちにさせることを忘れずに♫
企業のプレゼンみたいなイメージで。
⇩教員向けの書籍ですがたくさん事例がありそうです
- 本やアニメのキャラクターについて「ランキング発表」もおすすめ
これも、本やアニメを知らない先生が読んだら「この本読んでみたい!アニメ見てみたい!」
と思わせるように文章を工夫するのが大事♫
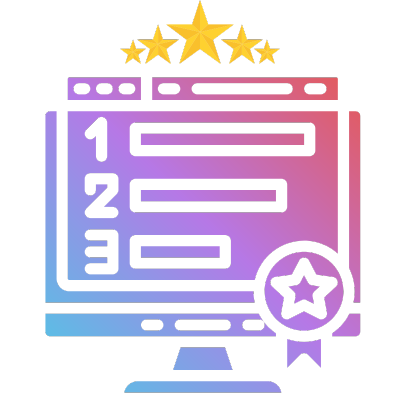
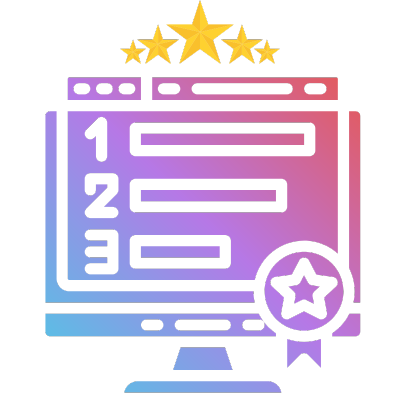
⑤「日記形式」や「クイズ形式」もアリ!
自由な形で表現することも、
自主学習の大きな魅力。
「書く=勉強」ではなく、「書いて伝える」楽しさを大切にしましょう。
- 「今日はなにを学んだ?」を1〜2行の日記に
短くまとめるのがポイント!長くてもいいですが、ダラダラ書きすぎないようにしましょう。
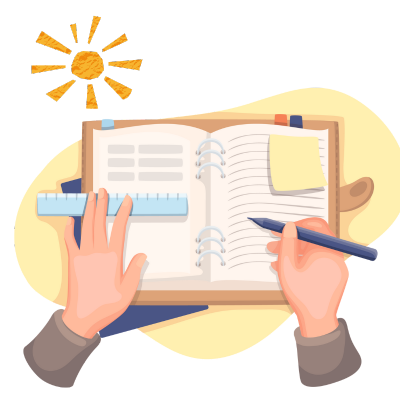
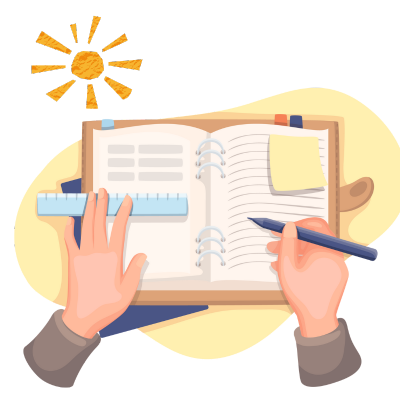
- 家族に出題する○×クイズを作る
「クイズ」という響きは子どももテンションUP!
家族に出題することでコミュニケーションの時間にもなります。
クイズの結果を記録するのも面白いですね。
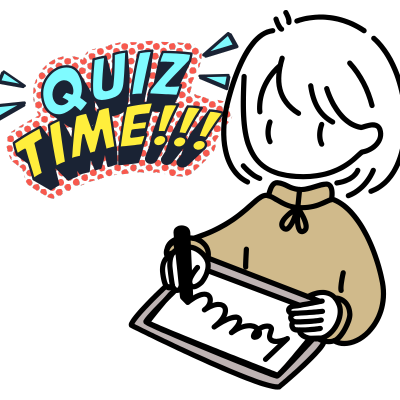
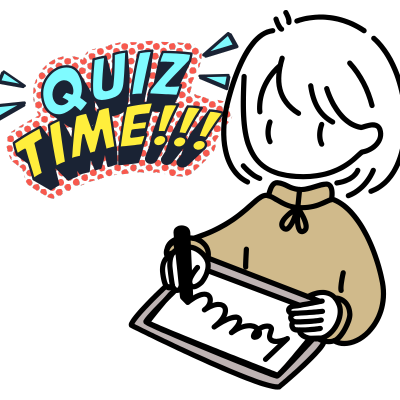
- 「なぜ?」と思ったことを調べて、自分なりにまとめてみる
こどもは「なぜ?」を探す天才だと思います。疑問や好奇心は、学びの原点。大切にしたいですね!
⑥ 1ページ全部を埋めようとしなくていい
「全部埋めなきゃ…」と思うと、内容が薄くなったり雑になったりします。
大事なのは、見やすく・読みやすくまとめる工夫です。
- 余白があっても「伝えたいことが伝わる」なら十分!
余白も「見やすくする」上では大事なポイントです。
- 絵や図、グラフを使って見やすくまとめる
絵や図、グラフを書くのは、文章を書くよりも意外と難しかったりします。
読む相手のことを考えて「どのように書いたら相手が読みやすいか」がポイントですね。
- 見出しをつけたり、色を変えたりする工夫もOK
3,4年生くらいになると「新聞づくり」の授業が出てきます。
その際に、読む人が見やすいように考えて
「見出し」「色つけ」などいろんな工夫が必要であることに気づくと思います。
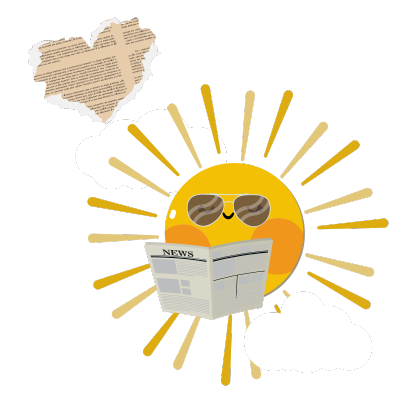
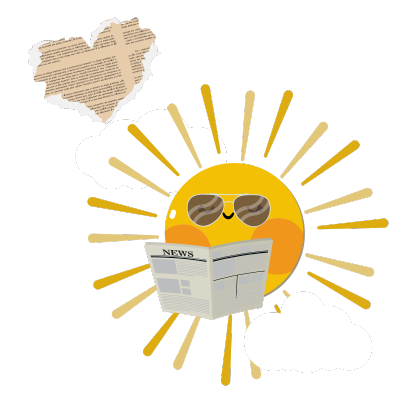
⑦ 「毎回違うこと」じゃなくてOK!
毎回テーマを変える必要はありません。
「同じ形式」で取り組むことで、学習習慣が身につきやすくなります。
- 毎週「今日の漢字3つ」「計算練習5問」などパターンを決める
あまり多すぎると大変なので、少なくてもOK!
自分ができる量を、自分で調整するのも大事な力です。
⇩フォロワーさんに人気の漢字辞典を使うのもおすすめ
- 「好きなこと調べ」をシリーズ化
「自分の好き・得意」を見つけることは、将来の職業や進路に大きく影響します。
たくさん見つけられるといいですね。
⇩うちのコもよく読んでいます!オススメです。
- だんだん工夫や深まりが出てくるので、成長が見えてきます
最初はうまくできなくて当たり前。コツコツ続けることが上達への近道だと思います!
⑧ タイトル・日付・名前を書く習慣をつける
どんなに内容がよくても、書き出しが整っていないと評価されにくいことも。
シンプルでよいので、決まったスタイルを身につけましょう。
- タイトルは「今日の漢字」「調べたこと」などシンプルに
タイトルを付けるのも意外と頭を使うところ。
相手がそれを見て、今日の学習内容がわかるような言葉を考えるのがポイント。
慣れてきたら「面白いタイトル・キャッチコピー」などを考えられるといいですね♫
- 日付と名前はノートの右上など、いつも同じ場所に
めんどくさいですが、これも見る人のことを考えると必要なことです。それに気づけると良いですね!
- 最初は「ひな形」を用意してあげると安心
私が作成したこちらも参考になると思うので、よかったらご覧下さいね!
⇩こちらの一番最後のページにまとめプリントがついています
⑨ スマホ・動画・AIに頼りすぎない
調べるのは簡単でも、写すだけでは力がつきません。
子ども自身が「考えて書く」ことが、学力のベースになります。
- スマホで調べたら、ノートには「自分の言葉」でまとめてみる
「自分の言葉」というのが難しいですが、何度も繰り返しやっていくことで徐々にできるようになります!
コツコツ続けていきましょう。
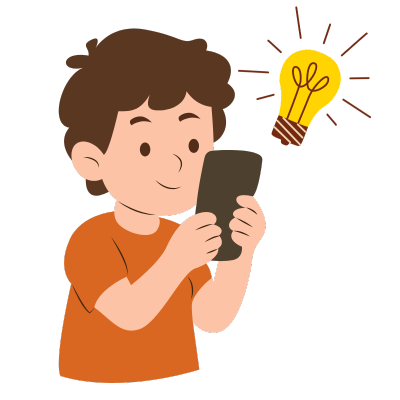
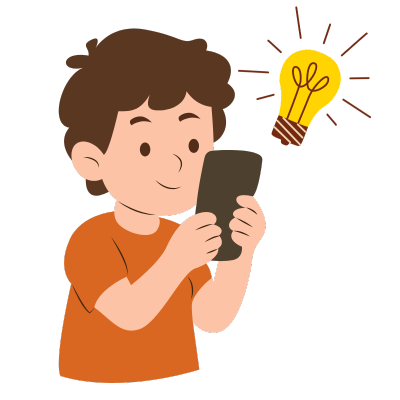
- AIが出した答えも「どこが面白い?どこが違う?」と考える力に
子どもたちがおとなになるときには、
AIが今よりも身近になっているのではないかな、と思います。
大事なのは「AIを使いこなす力」
を身につけることだと思うので、
普段からAIに触れておくことも大切なことかもしれません。
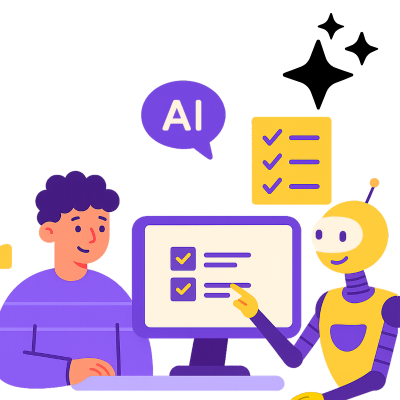
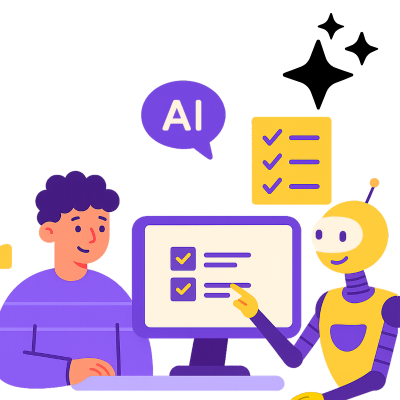
- 紙の辞書や図鑑を使う体験も大切に
ある研究では紙の辞書で調べた言葉のほうが記憶の定着が長かったというデータも出ているようです。
紙の辞書と、PCで調べる作業とをうまく使い分けていきたいですね。
⑩ おうちの人は「先生」じゃなく「応援団」
つい「直したくなる」「やらせたくなる」気持ちはありますが、
自主学習は「自分からやる」が最優先。応援スタンスで見守りましょう。
- 書けたら「わあ、がんばったね!」とまず声をかける
- 内容の良し悪しではなく、「やったこと」を喜ぶ
- 「つづけてるね」「じぶんで考えたんだね」など、努力を認める声かけを


📌 まとめ
- 自主学習は「自由=不安」になりやすい
- 最初は「まね」や「好きなこと」から始めてOK
- 1ページを埋めるより「考えて書く体験」を重視
- 親は“評価者”でなく“応援団”の立場で寄り添って
ぜひ、いろいろな方法を試してみてくださいね!