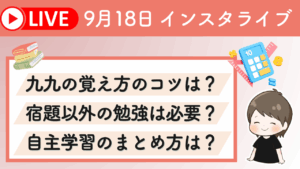〜低学年の計算力を育てる大切なステップ〜
実は「指を使って計算すること」には、
大切な意味と役割があります。
低学年のうちは、無理にやめさせる必要はありません。
🔸結論:指を使うのは自然な学びのステップ!
小学校1・2年生の子が、たし算やひき算を指で数えているのを見ると、
「このままで大丈夫かな?」と心配になる保護者の方も多いと思います。
でも安心してください。
🔹指を使うのは、頭の中の数のイメージ(数概念)を育てる大事な時期のサインです。
🔹これは、誰もが通る“発達の階段”の一部であり、決して間違った方法ではありません。
✅なぜ指を使うの?
子どもはまだ「数字=量」のイメージが育ちきっていません。
そのため、
- 5+3といっても「5」の次に「3つ分」進める感覚がまだつかみにくい
- 頭の中だけで処理するのが不安なので、「見える」「触れる」方法=指を頼る
こうした操作しながら考えることが、数の世界を理解する第一歩になります。
✏️こんなふうに声をかけよう
「指を使ってるけどいいの?」と感じたとき、次のように声をかけてあげると安心して学習できます。
- 「うん、いいよ!ちゃんと自分で考えてるね」
- 「今は指で考えていいけど、だんだん頭の中でもできるようになるよ」
- 「じゃあ、次は頭の中でできそうかな?やってみる?」
🚦いつかやめさせるべき?
子どもはある程度慣れてくると、自然と指を使わなくなります。
なぜなら、指を使うより頭の中で処理したほうが「早くてラク」だからです。
ただし、以下のような場合は少しサポートが必要かもしれません。
⚠️要チェックリスト
- 指を使っても答えが間違うことが多い
- 10以上のたし算やひき算でも必ず指に戻ってしまう
- 数字の読み書きそのものが不安定
→ これらに当てはまる場合は、数の理解がまだ不十分な可能性があります。
具体物を使ったり、数カード・10のまとまりなどで「数のイメージ」を強化するのがおすすめです。
✅指を使わなくても計算できるようになる5つのコツ
① 「10のまとまり」をしっかり覚える
👉 10になるペア(1と9、2と8…)は、すべての計算の土台です。
【家庭でできること】
- 「10になる組み合わせカード」で遊ぶ
- 「いくつといくつクイズ」(7と何で10?)を毎日5問ずつ
- お風呂や移動中に「10ゲーム」(交互に言って合計が10になったら勝ち)
⇩人気のピコトレを使うのもあり
② おはじき・積み木などの「具体物」で体験する
👉 数の操作を頭の中でイメージできるようにするための大事な準備段階です。
【家庭でできること】
- 5個+3個などを目で見て、手で動かして、「なるほど!」を感じる
- 計算式を読んで、ブロックや豆で実際に並べてみる
- 「動かして→読む→書く」3ステップで練習
⇩100玉そろばんはわかりやすいと思います
③ 「数直線」を使ってジャンプで計算
👉 指の代わりに「目でジャンプ」する練習です。
【家庭でできること】
- 数直線(0〜20くらいまで)を紙に書き、
→「5から3つ進む」などをペンや指でジャンプする練習 - だんだんイメージだけでジャンプするように促す
数直線の問題は苦手な子が多いので、早めに慣れておくとあとがとってもラクですよ♫
④「大きい数から数える」習慣をつける
👉 1+7より、7+1のほうがラク!と気づけるように。
【家庭でできること】
- あえて順番を入れ替える問題を出して、「どっちがやりやすい?」と聞く
- 「7に1足したら8だね、早いね!」と声かけで気づかせる
- たし算カードを逆順でも練習
⇩こんなポスターもオススメです
⑤「頭の中でイメージする練習」を少しずつ
👉 数の動きを頭で描けるようになってくると、自然と指がいらなくなります。
【家庭でできること】
- 「手は使わずにチャレンジしてみよう!」の声かけ
- うまくいったら「すごいね、もう頭でできたね」としっかり褒める
- 難しいときは「いいよ、今日は指でもOK!」の安心感も忘れずに
⇩100玉そろばんを使うのもオススメです
🌱まとめ
今は、指を使っていても大丈夫!
ただし、「だんだん指が減ってくる」「頭の中でできるようになる」が目標です。
そのために、
- 急がずあたたかく見守る
- 計算を体で感じられる経験(おはじき・ブロック・カードなど)を増やす
- 子どもの「できた!」を一緒に喜ぶ
こんなサポートが、計算力の土台づくりにつながります。